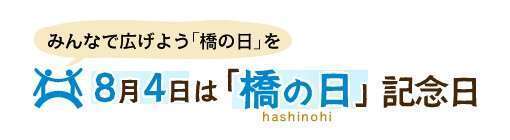今日は「橋の日」。1986年(昭和61年)、当時、橋梁(きょうりょう)会社に勤務していた湯浅利彦(ゆあさ としひこ)氏の提唱により生まれ、宮崎「橋の日」実行委員会が制定。日付は「は(8)し(4)」(橋)と読む語呂合わせから。意外と最近に制定されたんですね。東京JAPANで橋と言えば、「日本橋」。もともと江戸時代の1603年(慶長8年)に江戸の町割りを新たに行った際に、架けられた木造の橋で、後に何度も焼け落ちるなどして、何代にもわたり掛け替えられた。現在のものは1911年(明治44年)に完成したもので、日本橋川に架かり、石造りの2連アーチ橋となっている。江戸時代から東海道の基点とされ、現在は橋の中央に「道路元標」が設置されている。全国にある道路標識の「東京」への距離、50kmとかの表示は日本橋までの距離が記されています。

車で素通りしてしまう事が多いのですが、よくよく見ると、日本橋は獅子や麒麟の像、親柱に施されている松と榎の浮き彫りなど、装飾も素晴らしいです。これらの装飾には意図が込められているようで、たとえば獅子は守護を表し、両端に配された獅子像は東京都の紋章を前足にかけ、東京を守っていることを表現している。制作にあたっては、奈良県の手向山八幡宮の狛犬や、ルネサンス期のイタリア人彫刻家・ドナテッロのライオン像などが参考にされたようです。麒麟は吉兆を示す伝説上の霊獣で、東京の繁栄を象徴している。麒麟像の制作では、角の数に諸説があるため、何本にするか論争が巻き起こったという。松と榎の浮き彫りは、日本橋が江戸時代、五街道の基点だったことに由来する。各街道には1里(約4㎞)ごとに塚(一里塚)を築き松や榎を植えられ、マイルストーン(距離の標識)とされていたからだ。これらの彫刻は青銅製で、太平洋戦争中に金属が不足した折、供出の危機に見舞われたが、終戦によって難を逃れたといわれる。 我々世代にとって、「橋」と聞いたら一休さんです。この橋わたるべからず。のど真ん中を突き進む一休さん。この端をわたるべからず。。しびれた子供達は沢山いました。 慌てない慌てない、一休み一休み。本日もくれぐれもご健康でご安全に。
信じるか信じないかはあなた次第。
--------------------------------------------------------------------
世田谷区のGUARANTEE株式会社は三軒茶屋の建築内装屋です。
インスタやってます。
https://www.instagram.com/guarantee.tokyo/
法人・個人様を問わずオフィス移転やレイアウト変更。
各種内装仕上工事、設備工事。電気工事。
家具の組み立てやお部屋の模様替え等、
さまざまなご要望に柔軟対応しておりますので、
お困りの際はぜひご相談いただければ幸いです。
-------------------------------------------------------------------